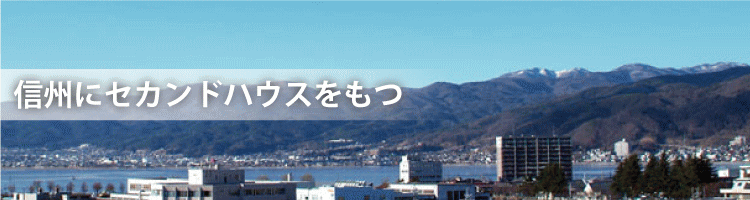飯田地域のご紹介

飯田地域
信州で最も南にある市で、南信州広域連合を形成する最大の自治体です。長野県内に5都市存在する人口10万人を超える市のうちのひとつで、南信地方では最大の人口を擁します。県内では長野市、松本市、上田市に次ぐ4位となります。
江戸時代には飯田藩の城下町として栄え、現在はりんご並木・人形劇の街として発展。城下町の面影を残す町並、今にも残る伝統芸能の多さから南信州の小京都となっています。また「環境文化都市」として太陽光発電などにも力を入れています。
江戸時代には飯田藩の城下町として栄え、現在はりんご並木・人形劇の街として発展。城下町の面影を残す町並、今にも残る伝統芸能の多さから南信州の小京都となっています。また「環境文化都市」として太陽光発電などにも力を入れています。

気候
気候は、長野県内で最も温暖な気候です。
一日の寒暖差が大きいのが特徴です。
気候は、長野県内で最も温暖な気候です。
一日の寒暖差が大きいのが特徴です。

南アルプスと中央アルプスに挟まれた本市域中、天竜川最下流部から南アルプスの聖岳まで、標高差2,700mを超える日本最大級の谷地形の中に、何段にも形成された段丘や、日本で一番長い断層である中央構造線が刻んだ遠山谷などがあります。
かおり風景100選
〔りんご並木〕
飯田のりんご並木は、かつての「飯田の大火」の復興過程で当時の飯田市立飯田東中学校の生徒達の提案により生まれ、今日まで営々と町のシンボルとして、彼らの手で守られ、育てられてきました。また並木通りは、大火の教訓から町の防火帯としても機能するように考慮されています。

飯田のりんご並木は、かつての「飯田の大火」の復興過程で当時の飯田市立飯田東中学校の生徒達の提案により生まれ、今日まで営々と町のシンボルとして、彼らの手で守られ、育てられてきました。また並木通りは、大火の教訓から町の防火帯としても機能するように考慮されています。

お練りまつり
大宮諏訪神社の式年祭礼(七年に一度)に合わせて行なわれているのが「お練りまつリ」で、大勢の人が街に出てねり歩くことから、こう云う様になったらしい。途中五十余年の休止の時期もあったが、正徳五年のひつじ満水の折、住民が大宮神社の神明様に加護を祈願したところ、幸に飯田の町は泥の海となる難をまぬがれた。領民はその神徳をたたえ、翌正徳六年の申年に中断していた祭りを再興し盛大に奉納するようになったと言われる。その出し物も年代により趣好がこらされた。
度々の火災で道具の大部分を消失してしまったが、大名行列や東野の大獅子舞などが伝統を受け継いでいます。

元善光寺
〔元善光寺縁起〕推古天皇十年に信州麻績の里(現在の飯田市座光寺)の住人、本多善光卿が難波の堀から一光三尊の御本尊様をおむかえしたのが元善光寺の起元で、その後皇極天皇元年にその御本尊様は現在の長野市へ遷座され、できたお寺が善光卿の名をとって「善光寺」と名付けられました。それから飯田の方の当山は勅命によって、木彫りで同じ御尊像が残され「元善光寺」と呼ばれるようになりましたが、仏勅によって「毎月半ば十五日間は必ずこの麻績の古里に帰りきて衆生を化益せん」というご誓願を残されたとのことで、長野の善光寺と飯田の元善光寺と両方にお詣りしなければ片詣りと昔から云われる由縁です。

お問合せ先
元善光寺 事務所
〒395-0001
長野県飯田市座光寺2638
電話0265-23-2525